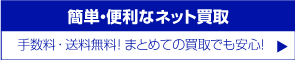By Kazuki Watanabe
プロツアーは“夢の舞台”である。
「出場したい」という夢を持つプレイヤーも多く、初めて参加したものは「またこの場所に来たい」と願う。そしてプロたちは「良い成績を残したい」「トップ8に入賞したい」「優勝したい」といった夢を抱えて、この会場を訪れる。
それは、取材という形で参加している私にとっても同じだ。
アイルランドのダブリンで開催されたプロツアー『霊気紛争』が、私にとって初めてのプロツアー取材であった。それ以来、アルバカーキ、ビルバオに足を運んだ。世界選手権2017も含めれば、今回が5度目の海外取材である。
プレイヤーとして参加することなど”夢のまた夢”である私にも、ライターとして、プロツアーで叶えたい夢がいくつもある。
そして私は、このプロツアー『ドミナリア』で、1つ夢を叶えた。
とあるプレイヤーに、インタビューを申し込んだのだ。
会場で彼を見かけた瞬間、まだ10代だったころの私が胸に抱いた、熱い想いが蘇った。
あの頃の私にとって、彼は憧れであった。強烈な印象と夢を与えてくれたプレイヤーであった。
マジックを紹介する冊子には、必ず彼の名前が記されていた。
「史上最強の男」。この称号に憧れなかったものは、きっといないだろう。
田舎で、まともな大会に出たことさえなく、ルールも適当に覚えたまま。マジックが”友人と放課後に遊ぶ道具”でしかなかった私にも、「これくらい強くなってみたいな」と思わせてくれた男。

カイ・ブッディ
カイ・ブッディである。
これまでのプロツアー取材で、彼に会うことはできなかった。会場を見渡し、スタンディングにも名前がないことを確認してから、「いつかインタビューできたら良いな」と、ため息混じりの夢を見るばかりであった。
ところが、今回は違った。会場でぼんやりとレジストの様子を眺めていた私の前を、彼が通り過ぎた。あのときの感動は、言葉にできない。
さて、このカバレージはHareruya ProsとHopesの活躍を追いかけ、伝える場所である。
私利私欲、と言われればそれまでだが、それで結構。批判は、甘んじて受け入れよう。
理由なんて、「目の前に、カイ・ブッディが居たから」だけで十分だ。
彼の言葉を日本語にして届けることに、私は価値があると信じている。
なお、インタビューをしながら、私は汗だくになっていた。こんなことは、生まれて初めてである。
何の誇張もしていない。それくらい緊張し、同時に感動したのだ。
あの頃のヒーローが目の前に座り、私に話しかけてくれるのだから。
史上最強の男、カイ・ブッディ
――「初めまして。お会いできて本当に光栄です」
カイ「こちらこそ、初めまして」
――「ええっと……すいません、とにかく緊張しています。10代の頃から、あなたは私にとってヒーローなんです」
カイ「そう言って貰えると嬉しいね。私が活躍……と言えるほどのものではなかったかもしれないが、トーナメントの最前線に居たのは数年だ。少し誇張されている部分もあるとは思うよ。でも、日本のプレイヤーが私を知ってくれているのは光栄だ」
――「久しぶりのプロツアーですよね? 前回はいつでしたか?」
カイ「前回は、プロツアー『カラデシュ』だったね。《密輸人の回転翼機》が大暴れしていたときだよ。というのも、去年は忙しくてね。南米からヨーロッパへ、引っ越しをしたんだ。これがかなりの大仕事で、残念ながらプロツアーには参加できていなかったんだよ」
――「そうだったんですね! おかしな質問だとは分かっていますが、プロツアーには何回くらい参加しているのですか?」
カイ「正確な数字は覚えていないが、たしか70回くらいだったと思うよ。初めて参加したのはもう20年前だ。もはや昔話の世界だね」
――「当時と比べると、マジックにも様々な変化がありました。一番大きな変化は何だと思いますか?」
カイ「そうだな……何よりもまず、Magic Onlineを始めとするオンラインの存在が大きい。今はすべての情報がオンラインで入手可能だ。最新の大会結果、デッキリスト、考察……そういったものがすべて手に入る。これは大きな変化だよ」
――「Magic Onlineが開始されたのは2002年ですから、当時はちょうど黎明期ですね」
カイ「そうだね。それに、昔はMagic Onlineに新セットが導入されるのが、とにかく遅かったんだ。新セットリリース後、しばらくしないとプレイできなかった。現在のようにオンラインの方が先にプレイできる、というのは別世界だね」
カイ「そして、“プロプレイヤーやチームの扱われ方”も大きく変わったよ。当時からプロツアーはあったし、スポンサードされていた者も居たが、単純に”プロポイントを所持している、トップレベルの層を評す言葉”だったからね」
――「なるほど。チーム、というのは昔から存在していたと思いますが、それが制度化されたり、スポンサードが当たり前のようになったり、というのは大きいですね」
カイ「そうだね。もちろん、当時の”強豪”というのは、必ず何らかのコミュニティに所属していた。交友関係が、強さだったのさ。たとえば、私はディルク・バベロウスキー/Dirk Baberowski、マルコ・ブルーメ/Marco Blumeと一緒にチームを組んでいたんだ」
――「おお……The Phoenix Foundation(※)ですね」
※The Phoenix Foundation: ドイツの強豪であるカイ・ブッディ/Kai Budde、ディルク・バベロウスキー/Dirk Baberowski、マルコ・ブルーメ/Marco Blumeの3名によって構成されるチームで、その戦績は枚挙に暇がない。現在でも名実ともに「MTG史上最強のチーム」として知られる。
カイ「よく知ってるね(笑) そう、The Phoenix Foundationだ。だけど、私の友人は彼らだけではない。その頃は、世界中の友人たちと、手紙で情報交換をしていたんだ」
――「て、手紙で!」
カイ「もちろん、手紙だから時間差はあった。だが、それが私の力の源だった。その手紙の束は、すべて保存してある。私の宝物だよ」
――「その手紙は、マジック界にとっても宝だと思います」
カイ「そうかもしれないね。シークレットテクが、本当の意味でシークレットとして存在していた時代さ。それが今や、あっという間に共有される。今回のデッキリストも、もう世界中に配信されているんだ。オンラインを駆使すれば、情報収集から練習、そして大会出場まで、すべてを1人で完結させることができるだろうね。紙のカードに一切触れずにマジックをプレイすることもできる。昔からすれば、考えられないことだよ」
カイ・ブッディが語る、マジックの魅力
――「20年以上に渡ってマジックに触れているわけですが、最大の魅力は何でしょうか?」

カイ「とても単純だが、何十年触れていても、楽しいんだ。これに尽きるよ。これだと言葉が足りないから、私が”楽しい”と思う理由をお伝えすることにしよう」
カイ「マジックは、常に違ったゲームに出会うことができる。私はこれまでに数え切れないほど対戦をしているわけだが、同じゲームが二度繰り広げられることは一切ない。これは、すごいことなのさ」
カイ「例えばチェスの場合、序盤の動かし方にはある程度の決まった形がある。少し慣れたプレイヤーならば、『ああ、この始まり方か』と思うわけだ。しかし、マジックにはそれがない。相手がプレイする土地、呪文はゲームごとに違う。こんなゲームは他にないよ。そして、今でも新しいカードが発売されているんだ。『ドミナリア』の発売に心躍らせたプレイヤーは多いだろうが、私もその一人だ。新しいカードや、デッキを見ると、今でも心が踊るよ」
日本の読者へメッセージ
――「では最後になりますが、日本にもあなたに憧れているプレイヤー、そしてファンがたくさんいます。彼らにメッセージをお願いします」
カイ「プロツアーやグランプリで、日本のプレイヤーから声を掛けられることも多い。毎回、驚いているよ。当時の私は、ただひたすらこのゲームを楽しみ、勝つことを目指していた。そして、様々な栄光を勝ち取ることができたわけだが、それがどれほど周囲に影響を与えたかは未知数だったんだ。君は言ってくれたね、『ヒーロー』と。こんなに誇らしいことはないよ。私がこのゲームで得た栄光やトロフィーの数よりも……少し恥ずかしい言葉だが、私に憧れてくれるプレイヤーの方が多いんだ。そういったプレイヤーに出会うことができることが、今となっては私の誇りだね」

カイ「日本にも偉大なプレイヤーが何人も居る。若いプレイヤーも多いようだ。私からメッセージを送るとすれば……とにかく、マジックを楽しんで欲しい。楽しんで、仲間を増やして欲しいね。マジックには、無限の可能性が秘められているんだ。きっと、君たちの人生をより良いものに変えてくれるはずだ」
ここで、インタビューは一段落だ。ここから私は、光栄にも彼と雑談をする機会を得たのだが……そこでの会話を綴るのは、やめておこう。あまりにも取り留めがなさすぎる。懐かしのデッキや、チームの思い出といった取り留めのない話を、時間が許す限り繰り広げただけなのだ。
とはいえ、どうにかしてこのエピローグを兼ねたインタビューを締めくくり、プロツアー取材を終えなければならないのも事実。こうやって彼との会話を思い出しながら悦に浸り、文字を打ち込んでいるうちに、フライトの時間が刻一刻と迫っているのだ。
最後に記すのは、カイ・ブッディが考える「プロツアーとは」。
カイ「君は、カバレージライターなんだね。出場を目指さないの?」
そう聞かれて、私は返答に窮した。冒頭にも記したとおり、それは”夢のまた夢”。はっきり言って、ありえない未来の話なのである。
だから私は、冗談半分で「プロのカバレージライターとして、参加したいんです」と伝えた。
そう、冗談半分で。だから、半分は本気なのだ。これからも夢を叶えるために、プロツアーに来たい。たしかに私はそう思っている。
すると、彼はこう言ってくれたのだ。
カイ「それは素晴らしい考え方だね。『プロツアー』というものの、あるべき姿だよ」
そして、満面の笑みを見せてくれた。それは、私が何度も何度も見てきたヒーロー、カイ・ブッディの笑顔そのものだった。
カイ「プロツアーというのは、プロプレイヤーが集う場所ではない、というのが私の考えだ。この場に居る全員が、自分の仕事をプロフェッショナルとしてこなす場所なんだよ。プレイヤーは、勝利を目指す。それがプロだからね。同様に、ジャッジ、スタッフ、そしてカバレージライターも、己の仕事に誇りを持ち、プロフェッショナルとして参加する。そうあるべきだよ」
私の半分を占めていた冗談は、綺麗さっぱり吹き飛ばされた。
席を立った彼が「今日はありがとう。これからもお互い頑張ろう」という言葉とともに、手を差し出してくれた。
その手を、私は20年分の思いを込めて、10代の自分と共に握り返した。
プロツアーは、“夢の舞台”である。
プレイヤーのみならず、この最高峰の戦いに関わるものすべてにとって、“夢を叶える場所”なのだ。
さあ、週末が終わる。夢が覚め、現実に戻る時間だ。
私はまたこの場所を訪れることを夢見ている。果たしてそれが許されるかどうか、今は定かではない。しかし、もしも許されるのならば。
彼との約束を違えぬように、精一杯の努力をするつもりだ。
それでは、また次回のプロツアーで。
▼プロツアー現地レポートトップへ戻る