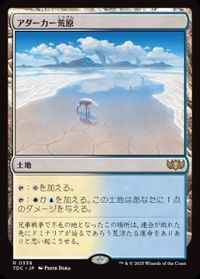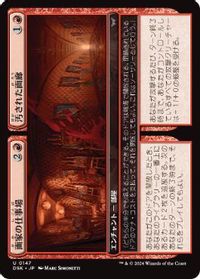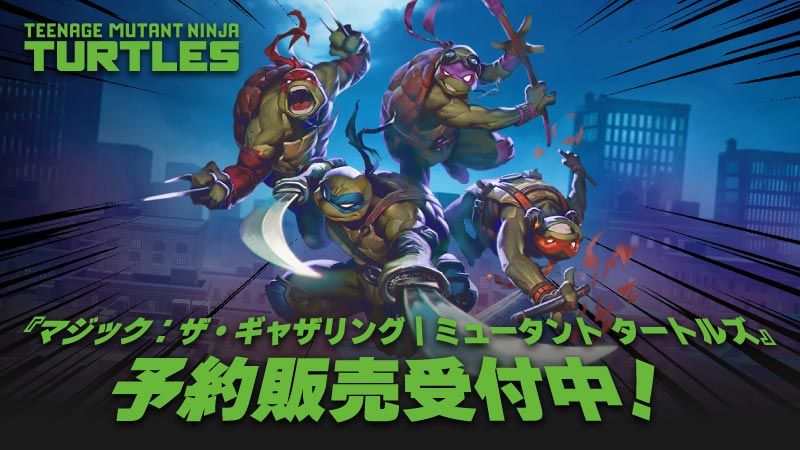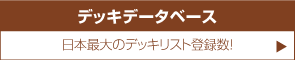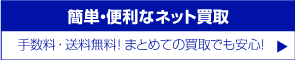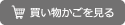はじめに
お久しぶりです。てんさいチンパンジー(@tensai_manohito)です。
先日、『チャンピオンズカップファイナル シーズン3ラウンド3』に参加しました。結果は13位で次回プロツアーの権利を獲得!2年ぶりの権利獲得で素直に嬉しく思います。
チャンピオンズカップファイナルday2。グリクシス。
— てんさいチンパンジー (@tensai_manohito) March 5, 2023
ジャンド ○○
青単 ××
赤単 ×○○
アブザン ×○○
ID
最後勝ってもtop8無いためIDで終了。
8-3-1で16位。800ドルとPT権利。デッキは微妙だったかも。 pic.twitter.com/go0fQORBsb
もう2年経つんですね……
今回は参加にあたって、どんな考えでどんな取り組みをしてきたのかを語る……要するに勝ち語りです。時系列順に取り組み方、当日のレポート、反省点、最後に使用デッキの最新リストを紹介します。
取り組み
今回は普段から集まっている仲良しグループ、通称「常勝集団MSD」で一緒に練習を行いました。
練習には市川 ユウキさんと井川 良彦さんも参加していましたが、両名ともすでに該当プロツアーの権利を持っているため、監督としてワチャワチャ参加。盛り上げ担当です。
練習といっても、やっていることは普段の集まりの延長。厳密にルールを決めてやっているわけではなく、画面を共有して情報を共有しながらマジックをする。ただそれだけでした。
地域CS練習も佳境 pic.twitter.com/DTrfPXQdnM
— Yuuki Ichikawa (@serra2020) April 27, 2025
スタンの調整、今日も盛り上がっております pic.twitter.com/SBpqMF4mc6
— Yoshihiko Ikawa (@WanderingOnes) April 28, 2025

初期デッキで戦う図。早く寝ましょう。
(manohito=増田、rerere=平山)
どんな流れで取り組んだのかをざっくり解説します。大まかに以下の流れに沿って進めていました。
■調整の流れ
[1] 環境デッキの精査(~2週間前)
[2] 使用デッキのアーキタイプ決定(~1週間前)
[3] 使用デッキの内容決定(~サブミットまで)
[4] 休憩(~当日まで)
[1] 環境デッキの精査(~2週間前)
最初は、各人が思い思いに気になるデッキをテストするフェーズ。このフェーズはとにかく人海戦術。ある程度の質は求められるものの、それよりも量を重視しています。
ほかの人がテストしていないデッキを選んでテスト&積極的に意見を交換し、デッキの感触を確かめていきます。
ここが徒党を組んで練習する一番のメリットと感じています。
この時点での各デッキの評価や感想について紹介します。
イゼット果敢:評価〇
従来の果敢戦略は、爆発力こそあれど除去に弱いという明確な弱点がありました。
しかし、『タルキール:龍嵐録』で登場した《コーリ鋼の短刀》のおかげでその弱点を克服。赤系アグロに負けず劣らずのスピード&爆発力を持ちつつも、《嵐追いの才能》や《食糧補充》を使ったロングゲームも可能という、文句なしに強力なデッキです。
ただ、当初はこのデッキに対して懐疑的でした。《コーリ鋼の短刀》は確かに強力ですが、赤系アグロに対して《選択》や《手練》などのドローソースを唱える余裕があるかは甚だ疑問です。
各種ドローソースのような”無駄”なアクションを取ることが、「《コーリ鋼の短刀》を強く使うためにデッキが弱くなっていないか?」という懸念もあり、最終的にはそれをテストすることになりそうだな……と、この時点ではふんわり思っていました。
赤系アグロ(グルール/赤単):評価◎
前環境からの覇者。『タルキール:龍嵐録』からは《コーリ鋼の短刀》や《光砕く者、テルサ》が入ったり入らなかったりで、強化があったかといわれると微妙なところ。大幅なアップデートはありませんが、もともとがほかのデッキより頭1つ抜けている存在だったので、これでバランスが取れたかなという印象です。
早い段階から使うことを否定する理由がなければ、このデッキを選びそうだなと思っていました。
イゼット果敢対策で《一時的封鎖》が増えると予想できたので、このデッキを選ぶなら《脚当ての陣形》が使えるグルール型にするつもりでした。
しかし、環境の高速化に伴って《亭主の才能》を置いている余裕がないことから、純粋なグルール型というよりは、赤単タッチ緑(採用するのは《脚当ての陣形》《探索するドルイド》のみ)をイメージしていました。
ジェスカイ眼魔:評価〇
『タルキール:龍嵐録』から《氷河の龍狩り》や《光砕く者、テルサ》の追加で安定感が上がって評価が大幅アップ。《略奪するアオザメ》とも相性が良く、不利マッチであるドメインズアーに対しても押し切るパターンが増えたことも好印象です。
私自身、このデッキをかなり気に入って、Magic Onlineの『Standerd Challenge』に参加して準優勝しました(実際は決勝でスプリット)。また、後日に同デッキを使用した方が優勝(スプリット)したりと、かなりの手応えを感じていました。
スタチャレ、ガンマ使って決勝スプリット。デッキ強かった💪 pic.twitter.com/HJANfMWuXh
— てんさいチンパンジー (@tensai_manohito) April 19, 2025
Split Standard Challenge w/ Jeskai Oculus, deck is hella fun, lost to aggro twice. Playing turn one Tralalero Tralala is the tech!!@fireshoes value tag, list from manohito. pic.twitter.com/0uyqHSpxHO
— Morango 🍓 (@CrazyMorango_) April 19, 2025
問題はマナベース。
現在のスタンダードはとにかくゲームスピードが早く、4ターン前後でゲームが決着することもままあります。そんななかで3色かつ序盤から動きたいデッキは「ファストランド」+「ダメージランド」の組み合わせになります。
この構成は、序盤にファストランドを引くかダメージランドを引くかで大きな差が出ます。
ダメージランドは1枚ならまだしも、2枚、3枚と重ねて引いてしまうと、どんどんダメージが嵩んでいきます。冗談抜きで土地からのダメージだけで8~12点ほど受けるゲームも発生しました。
そうなると、本来は有利であるアグロ系(イゼット果敢・赤系アグロ)に対しても落としかねないので、このあたりが解決すれば十分使用に耐えうるデッキになるなと思いました(マナベースそのものが解決することはないので、序盤からの色要求がそこまで高くない構成への変化があれば……)
ドメインズアー:評価×
どこまでいっても赤系アグロには弱く、ポジションデッキから脱することはないなという感想です。自身ではテストしていないものの、ほかの人が使っている感想を見ても微妙そうな反応だったこと、かつ赤系アグロが減る見込みもあまりないため、自分で使うことはなさそうと早い段階から切っていました。
エスパーピクシー:評価×
ジェスカイ眼魔同様、3色かつ1~3ターン目に動きたいデッキなので、「ファストランド」+「ダメージランド」の通称限界マナベース(?)を採用しています。これだけで使う気が失せるくらいには大きなデメリットです。
また、《コーリ鋼の短刀》の登場で除去コントロールのプランが成立しづらく、自分から動くことが求められる展開が増えました。
そうなると、《望み無き悪夢》《嵐追いの才能》への依存度が高くなる=マナベースの問題に加えて特定カードも要求されることになり、安定感は大幅に低下。
有利な相手も少なく、かつ土地事故による自爆で一定のゲームは落としやすい……とデメリットが目立ちます。使用を肯定する理由も見つからず、残念ながら使用候補には挙がりませんでした。
ジェスカイコントロール:評価×
ジェスカイ眼魔、エスパーピクシーと異なり、初動から動く必要がない3色デッキは「諜報ランド」+「境界ランド」の組み合わせになります。
一見、色は安定しているように見えますが、境界ランドから色を出すには諜報ランド(もしくは基本土地)が必要で、境界ランド側を固めて引くと満足に色が出ないという不具合がしばしば起きます。3種類採用している境界ランドの1色目がそれぞれで異なる色ならばまだ良かったものの、残念ながら1色目は白・白・赤で青が発生しません。
また、必要な土地枚数が多いのもマイナス要素です。ここまで何度か述べた通り、現在のスタンダードは非常に高速化しています。赤系アグロやイゼット果敢は4ターンキルも可能な上にデッキ全体が軽いカードで構成されているため、土地が2~3枚でスムーズに動けます。
それに対してジェスカイコントロールは、最低でも《道の体現者、シィコ》が唱えられる5枚まではストレートで必要ですし、ドローソースや打ち消しを強く使おうと思うとさらに土地が必要になっていきます。この時点で上位デッキに対してマリガン耐性の低さで差を付けられています。
そもそもクリーチャーは年々スペックが向上しているのに対し、対処する側のカードパワーはそこまで変化がありません。《熾火心の挑戦者》《コーリ鋼の短刀》を使うか《失せろ》《稲妻のらせん》を使うか選べといわれたら、残念ながら前者を選んだほうが勝率が出そうだなと思ってしまいます。
身も蓋もない言い方になってしまいますが、そもそもスタートラインに立っていないデッキだなという判断で没になりました。
ディミーアミッドレンジ:評価×
《悪夢滅ぼし、魁渡》《永劫の好奇心》が強力なミッドレンジデッキ。ただ、《心火の英雄》《多様な鼠》《熾火心の挑戦者》《コーリ鋼の短刀》など、パイオニア環境でも通用するレベルの低マナ域の脅威がそろっている現在のスタンダードで、わざわざ3~4マナ域で強力な動きがあってもな……というのが率直な感想です。
各イベントの勝率マトリクスを見ても、上位デッキに対して使用を肯定するような有利なマッチアップもなく、個人的な興味もなかったので早々に見限りました。
アゾリウス全知:評価×
《アブエロの覚醒》から《全知》を釣ってそのまま呪文を連打するコンボデッキ。残念ながら最初からこのデッキを使うことはありませんでした。理由は単純明快。コンボ強度が低い。その一点に尽きます。
コンボデッキに求められる最も重要な要素として速度(キルターン)が挙げられます。アゾリウス全知は自分都合で最速で4ターンキル。これを早いか遅いかの判断は相対的=環境によりますが、現在のスタンダードでいえば”普通”です。アグロデッキが平気で4ターンキルしてくるなかで、それと同速というのはそこまで魅力は感じません。
かつ、《アブエロの覚醒》を素引きしつつ《全知》を墓地に落として、《全知》の設置後もドローソースが繋がらなければならないという要求値の高さ。
《全知》を置けても《噴出の稲妻》や《切り崩し》で妨害されて止まる可能性もあります。加えて、自分より早いアグロデッキに対しての相性を担保するカードが《一時的封鎖》しかなく、相手視点でもそれが分かっているので比較的容易にケアが可能です。
速度も並で妨害はそれなりに受けやすく、相性の悪い相手にはあっさり負けやすい。総じて、環境上位のデッキを押しのけてまで使う理由が思いつきませんでした。
ドメインズアーのような必勝レベルの相手が存在することは間違いないですが、環境上位にアグロデッキが多いことを考えると積極的に使いたいとも思えませんでした。
アゾリウスアーティファクト:評価?
平山さんを筆頭に熊谷さん、加茂さん、宇都宮さんあたりがお熱だったデッキ。私も早い段階で少しだけ回していましたが、イゼット果敢や赤系アグロにボコボコにされ続けて以降は特に触れず。
standard chalenge
— Rei Hirayama (@sannbaix3) April 26, 2025
身代わり合成機で7-0からスプリット
兄弟仲の終焉のない世界なら最強か… pic.twitter.com/Q3BmTL7fmG
平山さんはこのデッキをかなり気に入っており、Magic Onlineでは『Standerd Challenge』では優勝したりも(決勝はスプリット)、個人的な興味はなかったのでスルーしていましたが、シェア率の低さの割には異常な勝率が出ていたので、隠れ最強デッキだった可能性はあります。詳細についてはきっと平山さんが語ってくれることでしょう。
そのほか、誰かが見つけてきたり自分で作ったオモチャデッキをテストしたりなど。
ボロスピア
宇都宮さんが見つけてきて遊んでいたものを見て自分でもテストしました。面白くて半日ほど費やしましたが、感想は「普通のデッキ」でした。
意外と部屋(《画家の仕事場/汚された画廊》)が強いな……とかプラスの知見はあったもの、流石にイゼット果敢やジェスカイ眼魔を押しのけてまで使うことはないだろうと思い没に。
グルールカッター
グルールアグロで《コーリ鋼の短刀》を使いたくて自分で考えてみました(という名目で誰もが思いつく構成ですが)。
イゼット果敢と異なり《コーリ鋼の短刀》の誘発回数に限界があり、また《弱者の力》を唱えることにストレスが貯まり続けて断念。
[2] 使用デッキのアーキタイプ決定(~1週間前)
「[1] 環境デッキの精査」を受けて使用するアーキタイプを決定します。
使用候補に残ったのが「イゼット果敢」「グルールアグロ」「ジェスカイ眼魔」。これらはデッキパワーも申し分なく、使用してもされても強力なデッキだと感じたので、このなかから選ぶことにしました。
まずグルールアグロが脱落。コアパッケージである《心火の英雄》《多様な鼠》《熾火心の挑戦者》と《噴出の稲妻》《巨怪の怒り》には文句がないものの、残りの自由枠が本当に弱い。
どれも穴埋め的な役割しかなく、コアパッケージを引いたときとそれ以外を引いたときとで出力が大きくブレます。使えば使うほど、「引くところを引いたら強い」「意外と不安定」という負の感想が強くなっていきました。
また、相性についても懸念が残ります。ジェスカイ眼魔に対してはそのサイズ感から相性が悪く、相手の自爆以外では勝ちづらいです。また、《幽霊による庇護》でイージーウィンされることもしばしば。
有利と思われた対イゼット果敢についても、その実態はほぼ先手ゲー(一応、赤系アグロ側のほうが少し有利かなとは感じましたが、本当に誤差レベル)だったというのもマイナスなポイント。
《コーリ鋼の短刀》+《手練》《選択》を唱えている余裕があるのかという懸念も、《コーリ鋼の短刀》から出るトークンがあまりにも強すぎるため、多少のロスは関係なく押し切られてしまうというのも誤算でした。当然、ミラーマッチは五分です。引いたモン勝ちです。
出力にムラがあるという自身の問題に加えて、環境上位デッキに対する相性も微妙ということで、結果として没になりました。
残るは「イゼット果敢」と「ジェスカイ眼魔」の2択。正直、どちらを選択するかは悩みました。費やした時間でいえば圧倒的にジェスカイ眼魔のほうが長く、情で選ぶなら間違いなくジェスカイ眼魔でした。しかし、最終的にはイゼット果敢を選びました。
現在のスタンダードのデッキはどれもブン回りがあり、そして回ったときの出力は非常に高いです。なので、この評価軸(最大値)でデッキを選ぶことはできませんでした。
そうなると次の評価軸は「安定感」。色が少ないデッキ・軽いデッキは事故りづらく、長いラウンドを戦うのに向いています。
イゼット果敢は赤系アグロほどではないものの、2色に抑えられているため色は少なめ。手札事故やマリガンは意外と多いですが、環境のほかのデッキと比較した際にはまだマシなほうです(逆にいうと、現在のスタンダードのデッキは最大値を求めなければ勝てないものが多く、どのデッキも非常にマリガンが多いです)。
逆にジェスカイ眼魔はやればやるほど事故率が気になりました。色が出ない問題に加えて、ダメージランドによる自爆が看過できないレベルで発生。
環境の上位デッキにコントロールデッキやコンボデッキが多いのであれば問題なかったかもしれませんが、残念ながら目下の仮想敵はイゼット果敢と赤系アグロ。とても無視できません。
それをカバーするためにメインから《幽霊による庇護》を採用し始めたり……と、どんどんブレる構成になってきて、徐々に弱者の構成になっているなと感じるようになりました。
机上ベースではアグロ系のデッキに対して有利ですが、実践では自爆も込みでほぼ五分だったというのが決め手になり最終的には断念。
また、イゼット果敢を最多と想定すると、
といったようにカード採択が変化していくと予想できました。上記の2点がいずれもジェスカイ眼魔に対してクリティカルな変更になるため、その点も向かい風だったように思います。
……ということで、最終的には消去法でイゼット果敢に決定しました。
[3] 使用デッキの内容決定(~サブミットまで)
使用するアーキタイプが決定した後は、内容を考えるフェーズ。
先に開催されていたボローニャの地域チャンピオンシップのフィーチャーマッチや、イゼット果敢を回している配信者のアーカイブを倍速で流してプレイ指針やサイドボーディングを学びつつ、気になるカードを自分でテストして……というのを2日間ほど繰り返していました。
ボローニャの優勝リストは非常に完成度が高く、このまま使用しても不満はないレベルでした。この結果を受けてミラーマッチが増えることは明らかでしたが、それについて特に工夫を凝らすこともしませんでした。
ミラーマッチに勝とうとしてほかのデッキに勝てなくなっては本末転倒です。このあたりの考え方は前回、プロツアー権利を獲得したときの反省からも来ています。
「グリクシスミッドレンジの過去と現在と未来」より引用
いくら占有率がトップだからといって、所詮は約30%。それ以外に当たることのほうが多いのです。
(略)
今回のようにある程度ばらけていることが予想できているのであれば、あまりやり過ぎないほうがよいでしょう。
過度な寄せはミッドレンジの特徴である「メイン戦はどんな相手にも満遍なく戦えて、サイド後にアジャストする」という強みも損なわれてしまいます。今回はまさにそれで失敗した良い例といえるでしょう。反省です。
ミラーマッチを意識するならば、メインから《ドレイクの孵卵者》や《塔の点火》を採用すれば勝率は上がるでしょう。しかし、対ジェスカイコントロールや対アゾリウス全知にはガードを下げることになります。このあたりは、どこかが上がればどこかが下がるというトレードオフをどう捉えるか次第なので、正解があるわけではありません。
ただ、私は以下の理由でミラーマッチのガードを上げる必要はないと判断しました。
①《塔の点火》について
《噴出の稲妻》を《塔の点火》に変えても、結局は序盤の《僧院の速槍》やカワウソ・トークンに当てる展開のほうが多いのでそこに大きな差はありません。
《ドレイクの孵卵者》は大量に採用すると手札で重なった際にプレイするタイミングが被ってしまうのが弱く、採用枚数は2枚が主流です。そのためだけに《噴出の稲妻》を《塔の点火》に変えるのはイマイチと感じました。
また、《噴出の稲妻》を本体に唱えて《コーリ鋼の短刀》を誘発させるパターンはそれなりに発生しますので、そういったプレイが取れない点も気になりました。
②《ドレイクの孵卵者》について
《ドレイクの孵卵者》はミラーマッチの後手で捲りのカギとなるクリーチャーとしてポジションを確立しています。確かにミラーマッチでは強力ですが、《精鋭射手団の目立ちたがり》を減らすほどのパワーは感じませんでした。
《精鋭射手団の目立ちたがり》はプレイパターンが柔軟で、ミラーマッチの押しつけでも対コントロールで緩急をつける際にも強力です。重なってもまとめて「計画」しておくことで、同一ターンに一気にプレイできる点も素晴らしいです。
占有率によっては《ドレイクの孵卵者》《塔の点火》の採用を良しとすることもあるでしょう。しかし、今回のフィールドでイゼット果敢とそのほかのデッキでそこまで差が出るとも思えませんでした。
ただ、蓋を開けてみればイゼット果敢の占有率は約33%。私の想定よりも遥かに多い人がこのデッキを選んでいたことになります(私は20%前半、どんなに多くても25%くらいだと思っていました)。
それであれば、多少は《塔の点火》や《ドレイクの孵卵者》がメインでも良かったかもしれませんが、仮説からの構築の決定についての考え方に後悔はありませんでした(仮説の精度については反省の余地アリですが……)。
[4] 休憩(~当日まで)
デッキリスト提出後は2~3マッチしか回しませんでした。これ以降にいくら練習しても良い方向に転がることはあまりないと考えていて、逆に「××を採用すればよかった……」と不安になったときにどうしようもないので、余計なことはしませんでした。
最終的にサブミットしたリストになります。メインはボローニャの優勝リストから諜報ランド→島に変更したのみ。サイドはいろいろと変更しましたが、大きくバランスは崩さないことを意識しました。
私以外の練習メンバーもほとんどがイゼット果敢を選択することになりました。平山さん、加茂さんの2名がアゾリウスアーティファクトを選択。両名はミラーは不毛と判断してズラした形に。
ちなみに、私以外のイゼット果敢を選んだ人は全員《ドレイクの孵卵者》をメインに採用していました。このあたりの細かい採択は個人の裁量に任せていたので、一緒にやっているからといって同じリストで出そう!みたいな意志の統一はありません。最後に信じられるのは自分。それで良いんです(?)
当日の結果
■対戦結果
〇Day 1
赤単アグロ 〇〇
ラクドスミッドレンジ ×〇×
イゼット果敢 〇×〇
イゼット果敢 〇〇
赤単アグロ ××
ディミーアコントロール 〇×〇
イゼット果敢 ×〇〇
ジェスカイ眼魔 ×〇〇
〇Day 2
イゼット果敢 ×〇〇
イゼット果敢 ×〇×
イゼット果敢 〇〇
アゾリウス全知 〇×〇
Day1で6-2、Day2で3-1の合計9勝3敗で13位。賞金1100ドルとプロツアー権利獲得!熊谷さんも10位で同権利を獲得。仲間の勝利は自分のことのように嬉しく思います。
先手は多かったものの同時にマリガンも多く、負けたゲームのほとんどは先手の利を活かせずの自爆でした。逆に相手もマリガンも多く、現在のスタンダードがいかに序盤の攻防を重視しているのかを思い知らされました。ちょっと温い手札をキープしたら一瞬で負けてしまうので、マリガンが厳しくなるのも致し方ないかなと。
懸念だったミラーマッチは、6試合やって5-1と勝ち越し。唯一の負けはマリガン祭りで手も足も出ずでしたが、勝ったゲームも相手の事故やマリガンで差がついたこともあるので、総じてツイていたなという感想です。
反省点
良かったこと
優れたデッキを選べた
このあたりの精度の高さは徒党を組んで練習するメリットです。過去にもリビングエンドや脱出基地コンボを選べた際にも同じことを思いました。
一人で練習するとどうしても私情を挟みやすく、一番時間を掛けたデッキに愛着が湧いてそのまま使ってしまいがち。
私は特にそのきらいがあり、今回でいえばおそらくジェスカイ眼魔になっていたと思います。ただ、そこは多くの人の意見もあり、フラットな目線で判断できました。
《精鋭射手団の目立ちたがり》を4枚にしたこと
ミラーマッチは6試合。そのすべてでメインから《ドレイクの孵卵者》が採用されていました。たしかに何度か出されて強いとは思いましたが、そこが《精鋭射手団の目立ちたがり》でもきっと結果は変わらなかったなと思います。
結局、先手で順当に回るならどちらをプレイしても勝てますし、後手の場合はどちらをプレイしても普通に押し切られる展開がほとんどでした。
逆にディミーアコントロール、対アゾリウス全知では明確に《精鋭射手団の目立ちたがり》で良かったと感じました。
マナを立てているターンは「計画」でズラして力を貯める、《食糧補充》のタップアウトに合わせて唱えて速攻で一気にダメージを叩き込む……などの《精鋭射手団の目立ちたがり》というカードができる最大限の力を発揮してくれました。
これらは練習段階で出た感想と同じものでした。この結果を受けての感想も変わりません。結果的には《ドレイクの孵卵者》が有効な相手に当たる回数のほうが多かったですが、それでも今回の構築に不満も後悔も反省もありません。
悪かったこと
サイドボードの精査が甘かった
いつもは早い段階でデッキを決定し、試行回数を重ねてサイドカードの要否をカッチリ決めることが多いです。
今回はどちらかというとデッキを選ぶフェーズに時間を掛けたため、普段に比べるとこのあたりの精査が甘めでした。
特にサイドは微妙だなと感じるカードが多かったです。《叫ぶ宿敵》は中途半端だなと感じましたし、サイドイン回数も最も少なかったです。また、オルゾフピクシーに当たらなかったから良かったものの、いざ当たった際のin/outが合わなさそうだったため、《轟く機知、ラル》か《永劫の好奇心》は欲しいと思いました。
サイドプランもふんわりと決めていたのみで、細かいところは実践の中で考えようと事前準備を怠っていました。
・対ジェスカイコントロールで、サイド後にどの程度《噴出の稲妻》や《巨怪の怒り》を残すのか。
・対ジェスカイ眼魔で、サイド後に《陽背骨のオオヤマネコ》を入れるのかどうか。
カッチリ決めていたわけではので、試合の中で手探りで考えていました。2本目はサイドインして、微妙だなと感じて三本目は抜いたり…と、いざ当日になってブレることも多かったです。
準備できることは準備しましょう(当たり前)。
ほかのデッキを触らな過ぎた
私はかなり早い段階からイゼット果敢・赤系アグロ・ジェスカイ眼魔の3択になるだろうと思っていました。実際にテストした時間の内、9割超はこの3つのデッキをプレイしていた時間になります。
今回、優勝したオルゾフピクシーは一度も回していませんし、ほかの評価低めのデッキについてもジェスカイコントロール以外は0マッチ。ジェスカイコントロールについても5, 6マッチで諦めました。
権利獲得/上位デッキの中でもグルール昂揚のような、使用者の少なさに反して好成績を収めたデッキはちらほらあります。そういったデッキを早めに切り捨てず、最低でも数マッチは触っておけばよかったのかなと思いました。そのうえでイゼット果敢を選べればなお良かったです。
おまけ:最新版リスト
最後に反省を踏まえた最新版リストを紹介します。
リスト公開制の見せ用である《呪文貫き》はメインからサイドに。代わりに先手のゴリ押し、後手の捲りで役に立つ《洪水の大口へ》は3枚目を採用しました。
活躍機会の少なかった《叫ぶ宿敵》は抜いて《永劫の好奇心》《轟く機知、ラル》に変更。また、オルゾフピクシーの《分派の説教者》《黙示録、シェオルドレッド》用に《焦熱の射撃》に追加しています。
おわりに
『チャンピオンズカップファイナル』参加レポートは以上になります。
プロツアーの権利は獲得したものの、実際に参加するのは9月とまだまだ先になります。久々にパイオニアやモダンを…とも思いましたが、6月末には『マジック・スポットライト:FINAL FANTASY』が待っています。まだまだやるぞ、スタンダード!
増田 勝仁(X)
おすすめ記事
- 2023/09/15
- マッチアップの本質に迫る!~その相性判断、曖昧じゃありませんか?~
- 増田 勝仁
- 2023/08/30
- デッキガイドの読み方 ~自分に合った情報を読み取ろう~
- 増田 勝仁
- 2023/06/09
- 対策を乗り越えろ!~サイド後の向き合い方~
- 増田 勝仁