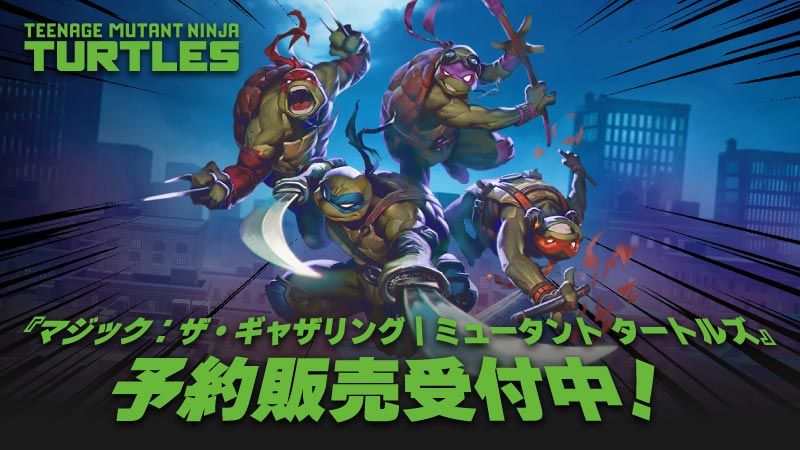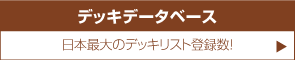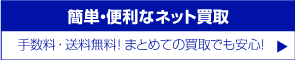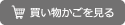はじめに
みなさん、こんにちは!イシバシです。
今回の記事では、『マジック:ザ・ギャザリング——FINAL FANTASY』からマジックを知り、かつ統率者戦に興味を持ってくれた方に向けて、「FINAL FANTASY VI」のお話を交えながらデッキの組み方などを紹介していきます。
なお、「統率者戦とは?」ついては、晴れる屋様でもいろいろな記事が掲載されているので、ここでは割愛させていただきます。
- 2025/03/18
- 完全にゼロからのスタート!今日から始める統率者戦!
- 紳さん
まず軽く自己紹介を。私は主にマジックのフォーマットのひとつである「統率者戦」でプレイしています。現在では晴れる屋様のイベント中心に参加しており、前回は統率者戦のプレイ指針についての記事を書かせていただきました。
- 2024/11/28
- ベテランってどう考えてる?統率者戦の構築とプレイング!
- イシバシ
今回の題材である「FINAL FANTASY」については、特にFF6が好きで、そのなかでもロックとセリスが好きなキャラクターです!挙げればキリがないのですが、FF6はどのキャラクターも見せ場があるので、プレイしていただければきっと好きになるキャラクターが見つかると思います。
ときには、タワーディフェンスのようなパーティメンバーを配置し切り替えながら敵を迎撃するような場面もあるので、ゲームシステムも楽しめることでしょう。個人的には魔石を育てるのが好きでした!
- 2025/06/16
- 『マジック:ザ・ギャザリング——FINAL FANTASY』伝説のクリーチャーまとめ
- 晴れる屋メディアチーム
そんなわけで、今回の記事ではこのFF6のキャラクターである「ロック」をもとに、普段どんな感じで私がデッキを組んでいるか紹介します。FFコラボは統率者指定できるカードが凄い枚数ありますので、「好きなキャラクターはいるんだけど、どうやって組んだらいいのかわからない……」といった方の参考になれば幸いです。
とはいえ、マジック自体を初めて触るという方には、1からカードを買い集めて組むのは難しいと思いますので、市販されている統率者デッキを購入するというのもひとつの手段だと思います。あるいは、きっかけが友達に誘われたなどであれば、デッキを借りてプレイしてみるのもよいでしょう。
幸いにもFF6は構築済みデッキがありますので、まずは統率者デッキ『トランス・リアニメイト』について軽く解説させていただきます。

『トランス・リアニメイト』(赤白黒)
統率者デッキ『トランス・リアニメイト』解説
『トランス・リアニメイト』は文字通り、リアニメイト戦略を主軸にしたデッキです。「リアニメイト」というのは、墓地からクリーチャーを戦場に出すことや、そういった呪文またはデッキを指す用語です。
デッキ内に特に多いのは、「墓地を利用する」「カードを捨て墓地に送り込みながら新しいカードを引く」というもの。若干重たいクリーチャーが多いので、手札が滞るようならためらうことなくカードをプレイし、新しいカードを引きに行きましょう。コツは、もったいないと思わず「今プレイできないならどんどん墓地に送って前に進む」ことです!墓地は第2の手札くらいに思っておくとよいでしょう。
この統率者戦におけるデッキの「顔」とも言うべき統率者になれるキャラクターは、《魔導の力を持つ少女、ティナ》と《ルーンナイト、セリス》の2人です。
ここ、どうしても語っておきたいポイントなので先にちょっと失礼します。FF6は仲間を集めながら、道中、いろいろな事情で一時的に離れたり、協力したりしながら進んでいく話なのですが、そのお話の序盤の中心になるのが「ティナ」であり、途中のターニングポイント以降の話の中心を務めるキャラクターが「セリス」です。このあたり、”大変わかっている”ポイントだなあと感心しました。
実は、FF6はスポット参加キャラクター以外にも序盤には仲間にいたのに後半では「仲間にしなくてもクリアできてしまう」キャラクターがいます。これは完全に個人的な感想なのですが、こうしたストーリー背景を知っていると、手札をグルグル循環させ、仲間と出会ったり離れたりを繰り返して勝利を目指すこのデッキは、FF6のストーリーをよく表していると感じます。
ちょっと言い過ぎたかもしれません。話を戻すと、カードとしてのティナは序盤から最後まで墓地を肥やしてリアニメイトできる完結型で、セリスは手札と墓地を循環させて墓地を使うとメリットのあるカードを引き込んだり、価値を高めたりするカードです。
このデッキをそのまま使うのであれば、最初のうちは素直に《魔導の力を持つ少女、ティナ》を選択すると使いやすいでしょう。《ルーンナイト、セリス》のほうは、すでにトーナメントレベルでも期待されている統率者になります。強力なサポートカードが多数ありますので、彼女の主戦場はそちらになるかもしれません。
この『トランス・リアニメイト』には、一見手札を捨てることがデメリットに見えるようでも、それをフォロー、あるいはそれを利用するためのカードがたくさん採用されています。
初心者のうちは、自分の手札や盤面に加えて墓地までも管理しないといけないのは大変かもしれませんが、相手のカードを使ったりすることもできるデッキですので、使っていて飽きのこないデッキになっていると思います。
カード単体を見ていきましょう。特筆すべきは《再活性》が収録されていることです!これは構築だけでなく、トーナメントでも使われるレベルのカードです。
相手のカードも戦術に組み込むことができるので、思わぬシナジーを形成したりとプレイヤーの腕が試されるカードでもあります。もし盤面や効果の把握が難しいようなら、無理をせず自分の墓地のカードを使うとよいでしょう。それでも十分に強い動きができるように構築されています。迷ったら、次に繋がるカードを選んでください。
たとえば、《怒りの雪男、ウーマロ》などはドローだけでなく状況によって効果を使い分けられるかなり便利なクリーチャーですし、FF6のボスである《混沌もたらす者、ケフカ》などは一度戦場に出てしまえばかなり強烈な効果を発揮するクリーチャーです。ただ、こうした激しい能力のカードは相手の除去の的になりやすいので、プレイするタイミングには十分注意しましょう。
《ロック・コール》
ここまで構築済みデッキを紹介してきましたが、ゆくゆくは自分の好きなキャラクターで遊んでみたいものだと思います。そこで、冒頭に挙げた私の好きなキャラクターである《ロック・コール》を基に、どんな考えでデッキを組んでいるかをご紹介していきたいと思います。
伝説のクリーチャー ― 人間・ならず者
接死、絆魂
ロック・コールがプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたび、あなたはカード1枚を引き、その後、カード1枚を捨てる。
まずはカードの能力を読みましょう。ときおり、カードテキストに事実上何も書いていないような伝説のクリーチャーもいるにはいます。が、その点でいえば《ロック・コール》はカードが引けるので十分仕事ができるクリーチャーです!
普通に統率者戦をプレイしていると、土地やマナファクトばかりで盤面に影響するカードも勝ちに行くカードも引けないような、「手が止まってしまう」状況になってしまうことがあります。ですが、1枚でもカードが引ける統率者というのは、いるだけで「とりあえず前に進むことができる」のです。
極論、土地しか引けなくても、《ロック・コール》がコンバットを続けていればいつか引き込むことができますし、戦闘で相討ちを取られても、その余ってしまったマナで再度キャストしなおすことができるのでフラッドも受けれるというわけです。
とはいえ、《ロック・コール》はスタンダードリーガルのアンコモンクリーチャー。書いてあることはどれも無駄にならないものではありますが、戦況を変えられるほど優秀なテキストではありません。単純比較で言えば、そのまま手札枚数を増やすことができる《織り手のティムナ》のほうが強いことは誰の目にも明らかでしょう。
しかし、テキストに書いてある、「カードを1枚引き、その後、カードを1枚捨てる」。ここがこのカードの個性です。《織り手のティムナ》にはできない、カードを引いたうえでさらに手札のカードを墓地に“置くことができる”のです!
基本的に、統率者を選定してデッキを組むときには、この「全肯定」のスタンスでいてください!あなたが選んだ統率者は、ゲーム中ずっとあなたの味方で居続けてくれます。なので、あなたも統率者領域に置いている間は、その統率者の味方で居続けてあげてください!
さて、統率者の個性が見えて来れば、あとはデッキのコンセプトが見えてくると思います。ここはやはり、墓地に送り込んだカードを復活させて戦うデッキにしたいところです。これならロック自身の旅の目的にも合致していていい感じです。
サンプルリスト
- 2025/05/27
- 「ブラケット」で統率者戦を楽しく!あなたのデッキはどんなかんじ?
- 晴れる屋メディアチーム
- 2021/10/21
- カジュアルからガチまで。統率者のテーブルどう分ける?
- 晴れる屋メディアチーム
このリストは晴れる屋様のイベントで採用される「Battle」、あるいは「ブラケット3」程度を想定して作成しています。私はよくイベントに参加するので、50分~1時間の制限がある前提の構想で、どちらかというと前者である「Battle」よりの調整になっています。
そのため、《壊死のウーズ》コンボを採用していますが、あくまでも「《ロック・コール》の能力を軸にして戦っていきたい」がベースです。逆に、もう少し高いブラケットで戦いたいと思うのであれば《生き埋め》や《タッサの神託者》なども候補に挙がるでしょう。
さて前述の通り、《ロック・コール》が山札からハントしてきたカードが墓地に置かれたなら、それを復活させるのが目的になります。リアニメイトカードで釣り上げていきましょう。対象がどれもオペラ女優のような見た目麗しいクリーチャーでないのが心苦しいところではありますが、基本的な動きは『トランス・リアニメイト』と同じような形です。
ロックを出して、ロックで殴って、手札の質を高めて、重たいカードを墓地に送り、引き込んだカードで復活させて勝利を目指しましょう!
ちなみに、意識的に土地・マナファクトはやや多めに採用しています。とにかくロックさえいてくれれば、地味ながらも着実に、少しずつ前に進んで行けるデッキなので、事故が起きにくいように調整を目指しています。強力なクリーチャーを釣り上げることができたあとは、ロックの持つ接死と絆魂で脅威から守ってもらいましょう。
釣る先は、せっかくですから自分の好きなファッティを叩きつけるのが楽しいと思います!僕は《スカラベの神》がかつてフロンティアというフォーマットがあったころから好きで使っているので、だいたい初期の案には入っています。
個人的に今回オススメしたいのは2つ。まずは《淀みの種父》。これは実質ほぼ合法の《聖別されたスフィンクス》です。《解体爆破場》を起動するとなんかカードが引けます。こんな感じで、普段なかなか出番が作ってあげられないカードにスポットライトを当ててあげてください!
また、もし相手に干渉し過ぎるのがあまり好みでないのであれば、《蝕むもの、トクスリル》や《発展の暴君、ジン=ギタクシアス》なども抜き、《原初の潮流、ネザール》や《砂岩の予言者》などのドロー・エンジンを入れてあげるとよいと思います。
この辺りは、参加するコミュニティのレベル感、もっというと雰囲気などで調整するとよいでしょう。もし難しいなら、あなたが「負けても使ってて楽しい!」と思えるカードが一番後悔がないと思います。
2つ目は《隔離用構築物》。《ロック・コール》のようにルーティングで手札が増えない統率者にはうってつけのカードです。毎回リアニメイト先が引けるわけではないので、土地などを捨てるとそのままプレイできるので事実上ワンドローです。
また、《禁止》などのコストで捨てた打ち消し呪文をさらにその打ち消し合戦でプレイできたりと、見た目は地味ですがかなりいぶし銀な働きをしてくれます!《帳簿裂き》などと合わせてもいいですし、全肯定の気持ちだけでフォローできない部分は実際に補ってあげていきましょう。
余談ではありますが、こうした統率者を選択するときは、「付加価値を高め過ぎない」ことは留意してください。たとえば、《永劫の好奇心》などのコンバットついでにドローができるもの、《テフェリーの永遠の洞察》のようなドロー量をかさましするものは相性自体はいいのですが、同時に「《ロック・コール》を除去するメリット」を高めてしまいます!
上で述べたように、《ロック・コール》自体はそこまで強力なカードではありません。強いカードには除去が使われやすいのですが、進んでロックに除去を撃ちたいプレイヤーはいないでしょう。「強すぎない」ことはメリットと考えてください!それを強くし過ぎることはデメリットです。
なお、これも個人的な考えではあるのですが、こうした新しいデッキを組むときには、あなたがよくメインで遊んでいるデッキの「ファーム(2軍)」のような役割で考えてみるのも良いと思います。たとえば、僕は意識的にテストしてみたいカードを採用することが多いです。
今回でいえば、《限りない強欲》や《悪魔的助言》などです。これは対戦している方が使っていたり、普段使わないデッキの解説記事で紹介されていたカードでした。
検索サイトであれこれ調べて勉強するのも良いのですが、統率者戦は実戦で本当にいろんな局面や盤面に遭遇するものです。とにかく気になったカードは何かメモや画像に残しておいて、まず一度使ってみましょう!使ってみないことには、わからないことが多いものです。
逆に、理論上最強のはずなのに、実戦で使ってみるといつまでも手札でモジモジしてるだけのカードもたくさんあります。あなたのデッキのホントのトコロはあなたにしかわからないのです。なので、怖がらずにイベントなどに参加してみてください!普段と違う環境には、きっと新しい発見があるでしょう。
《トレジャーハンター、ロック》
では最後にもうひとつ、「高ブラケット」「Challenge」以降を見据えたデッキサンプルを作っていきたいと思います。ここはやはり、ロックとストーリー上の関係が深い常勝将軍、セリス・シェールを推したい……ところなのですが、こちらはすでに熱心なプレイヤーたちが研究を重ねています。
そのため、断腸の思いでセリスの構築は譲ることとし、もう1枚のロック、《トレジャーハンター、ロック》のサンプルリストを見ていきましょう!
サンプルリスト
伝説のクリーチャー ― 人間・ならず者
これは、これよりも大きなパワーを持つクリーチャーにはブロックされない。
ぶんどる ― これが攻撃するたび、各プレイヤーはそれぞれカード1枚を切削する。これにより土地・カードが切削されていたなら、あなたは宝物・トークン1つを生成する。ターン終了時まで、それらのカードの中から呪文1つを唱えてもよい。
こちらの《トレジャーハンター、ロック》は黒赤カラーの攻撃的な統率者です。コンバットすると4人の山札を切削し、土地が1枚でもあれば宝物・トークンを作り、そのターンだけその中から唱えてもよいというもの。かなり好意的に解釈すれば、1人で《秘儀を運ぶもの、パコ》《熱心な秘儀術師、ハルダン》のような動きができるということです。
また、攻撃を通す必要がないこと、事実上の「潜伏」を持っていることで、フラッとコンバットにいっても平気な点は評価したいところです。特に《ギルドの職人》や《対称な対応》《師範の占い独楽》を強く使える統率者です。山札というダンジョンからざくざくとお宝をハントしていきたい!
さて、こちらもリアニメイト軸にしてもよいのですが、高ブラケットを見据えるとやはり《むかつき》などの強力なカードは無視できないところ。また、《師範の占い独楽》を強く使える統率者なので、《ボーラスの城塞》なども欲張って入れたい。そうすると、黒赤でも「未来独楽(《未来予知》+《師範の占い独楽》)」ができるのだから……と、今回はそこを軸にしてみました。
《ネクロポーテンス》などのカードで大量に引き込んだ後も役に立つので、終始腐らないカードだといえます。
序盤はロックがめくったカードが重たいとプレイできないので、軽めのスペルを多く採用しています。とにかく次につなげるドローできるものを優先しているので、除去はやや薄めになっています。必要なら相手の山札からぶんどって来ましょう!
そんな流れで《むかつき》も意識して採用しているのですが、基本的にやりたいことは「黒赤の未来独楽」です。本来であればこれに特化したいのですが、高速環境にも対応できることは必要です。
なお、この未来独楽については《ボーラスの城塞》《神秘の炉》《実験の狂乱》のほかに、《語りの神、ビルギ》の裏面である《豊潤の角杯、ハーンフェル》でもほぼ同じようなことができます。
もちろんコスト軽減が前提なのですが、青系の専売特許ではないところを見せてやりましょう。《語りの神、ビルギ》は両面で役に立ってくれるカードであることは覚えておいてください。
また、ゲームチェンジャー・リストなしの中ブラケット仕様も作成してみました。こちらはより未来独楽に寄せています。よりロック「らしく」勝つならば、こちらの方向が合っていると思っています。
ちなみにどちらのデッキも実戦にて回してみた感想なのですが、意外と土地が落ちないな……とか、結構手が止まるな……とか、微細な手直しはまだまだ必要そうです。ただ、若い統率者というのはこれから伸びしろがあると考えてください!いきなり完成したデッキというのは存在しないですし、環境によって採用カードは変えていくべきです。
以前も書きましたが、最初にデッキを組む段階では気負いすぎる必要はありません。迷ったら自分の楽しいを優先しましょう!
このデッキも、1人回しはガチャガチャと動かせて楽しい(もともと私が好きなアーティファクトを詰め込んだだけともいえる)ので、もし黒赤を触ったことがあまりなければ、ぜひ《死の国からの脱出》などを毛嫌いせず練習してみてください!
慣れてくると対戦したときに相手の攻め方がなんとなくわかってきます。そうしたことを繰り返していくと、あなたのメインで頑張っている統率者の勝率も自然とあがっていくことでしょう!
ぜひ、デッキと共に自身の経験値も高め、統率者戦を戦い抜いていってください!
おすすめ記事
- 2025/07/07
- 『FINAL FANTASY XIV』のカードで統率者デッキを構築!『サイオンズ・スペル』改善案&《アルバート》《エメトセルク》徹底解説(えんぞー)
- 2025/07/01
- 『FINAL FANTASY XVI』のカードで統率者デッキを構築!ブラケット別に3つのデッキを紹介!(きよそね)