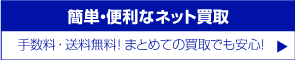はじめに
こんにちは、若月です。いやーすごいですね『統率者レジェンズ』!
これまでの『統率者』シリーズでも、古今東西の有名キャラクターが続々とカード化・現代スペックでリメイクされてきました。今年はそもそも新規レジェンドの枚数が段違いというのもありますが、プレビューではそれこそ毎日「あのキャラがついに!」とテンション上がりっぱなしでした。
いくらでも語れるラインナップ、けど今は先にこっちなのです。『灯争大戦』後日談のメインともいえるリリアナの顛末、前回の続きを小説「War of the Spark: Forsaken」(以下、Forsaken)から解説します。
ドミナリアに逃げたリリアナは故郷カリゴにて、廃墟となったはずの生家が綺麗に再建された様子を目にしました。そして、その館の主は「リリアナ・ヴェス」だと……。一方、リリアナ暗殺任務を請け負ったケイヤもドミナリアへ向かおうとしていました。
前回の記事
- 2020/10/26
- 第105回 『灯争大戦』後日談 リリアナ逃亡編
- 若月 繭子
『灯争大戦』 関連記事
7. 三人の出発
ケイヤが各ギルド代表者たちと暗殺任務について話し合っていたころ、テヨは慣れないラヴニカの街を彷徨っていました。昨晩、彼とラットはケイヤの好意でオルゾヴァに泊まったのですが、朝目覚めるとラットは姿を消していました。プレインズウォーカーではない彼女は、この先に待ち受けるであろう別れを悟り、一人去ってしまっていたのです。ケイヤは任務の話し合いがあるため、捜索をテヨに任せたのでした。
とはいっても、昨日来たばかりのラヴニカの街を知っているはずもありません。彼の思考はぼんやりとリリアナの件に戻ります。なぜギルドはリリアナの言い分を聞こうともせずに暗殺したがっているのだろう?そしてケイヤはなぜそれを受けたのだろう?いろいろと考えましたが、ケイヤは道理をわきまえた人物です。あとできちんとその話ができるだろうと彼は思っていました。
空を見上げると、太陽が1つだけ輝いていました。故郷ゴバカンにある2つの太陽を見慣れた彼の目に、それは寂しそうに映りました。そして、あらゆる種族のあらゆる人々がテヨには目もくれることなく何百人と通り過ぎていきます。故郷の砂漠で迷うよりも、この人混みの中で迷うほうがたやすいかもしれません。ラヴニカは驚異の都市、けれど今のテヨは冷たさを感じていました。空に浮かぶ1つだけの太陽のように、孤独に思えたのです。
気づくと彼は、ギルド渡りの遊歩道にやって来ていました。昨日、初めてのプレインズウォークでラヴニカに辿り着いた場所。そしてその直後、彼女に遭遇した場所です。ここでラットは自分を拾い上げ、怯えさせ、そして夢中にさせてくれたのでした。そのラットはどこに――いました。昨日とまったく同じように、柵に腰を下ろして。テヨと同じく、彼女も昨日の自分たちの出会いを考えていたのは間違いありませんでした。なぜなら、それを大声でまくし立てていたのですから。
小説「War of the Spark: Forsaken」チャプター21より訳
「あの子、ここにいたのよ。砂だらけで、猫が毛玉吐くみたいに咳してて。で、私はさ、ただ見てたっていうか。どこから瞬間移動してきたのかなーとか、次どこへ行くのかなーとか。そのときはまだプレインズウォーカーだって思いつかなくて。なんでかなー?って。でね、そこでなんと私に声をかけたのよ、私をじっと見て、『お願いです』って。それだけで私がどれだけ驚いたかわかる?この柵どころか歩道から落ちちゃいそうだった。多元宇宙からも落ちちゃいそうだった。あの子、私を見たの。私を、見たのよ」
いつもそうなのだろう、彼女の声を聞ける者は誰もいなかった。大声で独りごとを言うのはラットにとって当たり前のことなのだろう。彼はまくし立てられるその喋りが好きになっていた。ずっとそこに立って聞いていたかった。
「今考えてみると、あの子ってばあのときからほんとに素敵だったと思わない?けどそのときはまだ気付いてなかたんだろうなー。心の深いとこで気づいてたのかもしれないけど」
テヨは顔を真っ赤にし、すばやく咳払いをして自分の存在を明かした。「ラットさん?」
彼女はすぐさま振り返り、その表情には純粋なパニックがあった。そして隠れようとしたのか、柵から飛び降りて小さく屈みこんだ。そして手で顔を覆った、まるで子供が「いないいないばあ」をするように。
僕のことが見えないなら、僕にもラットが見えないと思っているんだろうか?
彼はその目前へと歩み出て、手をとった。「隠れるの、下手ですね」
テヨは彼女の手を引いて立ち上がらせた。「うん。だって……隠れたことなんてないから。私は隠れる必要とか全然ないから。けどそれ以外はいろいろ得意だよ、知ってるでしょ?」
「知ってますよ」
「いろいろね」
「いろいろですね」
「ごめん。あんなふうに出て行ってさ。けど私、さよなら言うのって下手なんだもん。そんな必要とか今までなかったから。そんなこと言うような相手はそんなにいなかったから。今もだけど」
ですが、ケイヤはラットを探すように頼んだのです。それが別れを告げるためなのかどうかはわかりませんが、ケイヤもラットの辛さは知っているはずです。では何のために?それは実際に聞くのが一番です。ラットはテヨと腕を組み、歩き出しました。
同チャプターより訳
ラットが口を開いたのは、橋を渡り切る前のことだった。「あのさ、テヨ君は黒髪さんを殺すべきじゃないって、本気で思ってるんだよね」
彼は一瞬驚いた顔を見せた。「はい。ケイヤさんは今やゲートウォッチの一員です。人々を守るって誓ったんですから。暗殺するのではなくて」
「けど、ヴェスさんを殺すことがほかの人を守ることになるとしたら?」
「少なくとも、ヴェスさんのほうの話を聞くまでそれはわかりませんよ」
「それもそうだよね」
「でしたら、ケイヤさんの説得を手伝ってくれますか?」
「きっと」
テヨは頷き、微笑んだ。
そうして2人はオルゾヴァへ戻ってきました。ギルドマスターの地位を一時的にトミクへ移譲する手続きが終わり、ようやくケイヤはラットに向き直ります。ドミナリアへ向かう前に、彼女はテヨを故郷の次元ゴバカンへ送っていくつもりでした。当然、プレインズウォーカーでないラットは一緒に行けないはずです……というところで突然、部屋が炎で満たされ、その中にヤヤが現れました。ヴラスカとビビアンを(ドビン追跡のため)カラデシュに案内し、ラヴニカへ戻ってきたのです。弱々しくふらついたヤヤをテヨが受け止め、椅子へ座らせました。
少し休んだらドミナリアへ案内するとヤヤは言います。ケイヤは「3人そろって」向かうつもりでした。3人。自身とテヨと、ラットです。彼女の孤独を知るケイヤは、ラヴニカに独り残していくつもりはありませんでした……とはいえ、プレインズウォーカーではない彼女をどうやって?
ここで一つ説明を。大前提として現在、プレインズウォーカーの灯を持たない有機体は久遠の闇を耐えられません=別の次元へ渡ることはできません。有機体、それは死んでいても同じです。ゾンビの軍勢である永遠衆がラゾテプ鉱石でコーティングされていたのは、次元間の輸送に耐える(《次元橋》を通る)ためでした。『灯争大戦』の結末で灯を失ったボーラスが牢獄領域へ行けたのは、ウギンの翼に包まれていたためと、ボーラス自身の耐久力によるものと思われます。それでも甚大なダメージを受け、意識を回復するまでに数週間かかったようです。ほかにもファートリが別の次元に食物を持っていこうとしたものの、プレインズウォークの間に塵と化したというような描写もありました。
ですがケイヤ曰く、自分はその例外なのだと。1人か1体を自分と一緒に霊体化し、一体化して久遠の闇を渡ることができる。それを発見したのは純粋な偶然によるもので、プレインズウォークしようとした瞬間に飼い猫が腕に飛び込んできたためなのだとか。ヤヤもラットも、信じられないというように声を上げました。前者は訝しむように、後者は喜ぶように。
小説「War of the Spark: Forsaken」チャプター24より訳
「一緒に……行けるの?」
「望むなら。けど言っておくけれど、体力をすごく消耗するし危険よ。それでも、すべて上手くいけば、リリアナ・ヴェスの暗殺任務を完了してあなたをラヴニカへ帰すこともできるでしょうね」
ラットは不満な様子のテヨを一瞥し、言葉を飲み込んだ。リリアナ・ヴェスの殺害に心から賛成ではなかった。あの女性がボーラスを殺したのだから。とはいえ、リリアナの手で多くのラヴニカ人が死んだのだ。グルール一族の掟に照らし合わせても、リリアナ・ヴェスは死に値する。だがセレズニア議事会としてどうかは定かでなかった。
また一方で、ラクドスとしての自分はその旅にぞくぞくしていた。そして何よりも、友達と一緒にいられるのだ。
ここでヤヤは、自分には見えない何かとケイヤが喋っているらしいと気づきます。多くの人には見えない人物がいると説明され、ヤヤは納得したようなしていないような様子でした。
一緒に連れては行ける、けれどとても危険なのは間違いありません。よく考えてとケイヤは言いますが、ラットはもう一緒に行くと決めていました。母に伝えるつもりもありませんでした。何週間も不在にするのはいつものこと。そしてもし道中で死んでしまっても、母はやがて娘がいたことすら忘れてしまうでしょう。悲しむこともない、それはそれで良いことなのかもしれないと。
話はまとまり、まずはテヨの故郷へ。ですが案内してと言われて彼は慌てました。覚醒したのは昨日のこと、まだ意識してプレインズウォークしたこともないのです。そこはケイヤが方法を教えてあげました。故郷のことを考えて、集中し、帰ろうと決める――ごく単純です。テヨは目を閉じ、そして白く透明な幾何学的図形を弾けさせて消えました。ヤヤが炎を発して難なく続き、そしてラットをしがみつかせてケイヤも出発していきました。
8. カリゴにて
……続きを話したいところですが、今はリリアナ追跡の話を進めるため、ドミナリア到着まで飛ばします。テヨは故郷ゴバカンの僧院へ帰りつくのですが、いろいろありましてケイヤたちと一緒に旅立つことになりました。ここのエピソードはとても良いのでいずれきちんと紹介したいのですけれどね。テヨが盾魔道士団の僧院に来ることになった経緯とか、同室の友達との切ない別れとか。いずれテヨが再登場するときに、かな?
ラットを連れたケイヤのプレインズウォークも、両者ともひどく消耗するという以外は特に問題なく実行できました。到着したのはカリゴの森、ヴェス家の廃墟から1マイル(約1.6km)もないところ。この場所へ連れてきたヤヤも疲れていましたが、長く居残る気はありませんでした。去り際、彼女は唯一元気なテヨに声をかけます。
小説「War of the Spark: Forsaken」チャプター40より訳
「それに、昨日ずっと永遠衆と戦ったあとだ。何もかも初めてのことで、疲れたんじゃないのか?」
彼は頷いた。「多分。ですが僕はまだやれます、その……何でも」
「そうか、若いね」ヤヤはケイヤのほうを頷いて示した。「見張っててやりな、あの子と……私には見えないもう1人の子も。回復するまでね」
「はい。約束します」
「テヨ・ベラダ、あんたを信じてるよ。僧院長さんは言ってなかったかもしれないけど、あんたはいい子だ」
テヨはその誉め言葉に驚いて呆然とした。ラットは笑わずにいられず、テヨは彼女を睨みつけた。
「その子、あんたを笑ってるのかい?」
「そうです」
「いいことだよ。おかげであんたはずっと正直で謙虚でいられるんだから」
テヨはこれまでの礼を言いましたが、ヤヤは少々不機嫌に返答してプレインズウォークで去っていきました。弟子であるチャンドラのこともあり、ヤヤはこの任務を決して支持はしていないのでした。
それからケイヤが動けるようになるまで約1時間を要しました。ラットはもう少し早く復活し、ゴバカンで拾い集めてきたダイヤモンドを数えていました。「金剛嵐」が吹き荒れるゴバカンではありふれたものですが、ほかの次元ではとてつもない価値を持つと聞いてテヨは驚きます。山分けをしながらじゃれ合う2人の姿に、ケイヤの心は癒されるようでした。
テヨは故郷が恋しいのではとケイヤは不安でしたが、自分たちとの旅を喜んでいます。特にラットが一緒にいることを。その理由をケイヤは、本人よりもよくわかっていました。ラットもこの旅を満喫しています。それ以上に、ケイヤは嘘偽りなくこの2人との旅を楽しいものと感じていました。純粋な心を持つ若者2人との旅は、この多元宇宙も悪いものではないと感じさせてくれたのです。
やがて3人は歩きだし、ラットは偵察のために1人先にヴェス家の館へと向かいました。テヨは何度か口を開きかけましたが、黙っていました。ケイヤは彼が言いたいことを察していました。
小説「War of the Spark: Forsaken」チャプター44より訳
「テヨ、言ってごらんなさい」
彼は少々驚いた様子だった。ラットに心を読まれるのは慣れていたが、ケイヤからは予想していなかった。
ケイヤは促すように続けた。「あなたがこの任務を良く思っていないのはよくわかるわ」
彼はかぶりを振った。「すみません。ケイヤさんとラットと一緒に旅ができて嬉しいのは本当です。それでも……これは、正当だとは思えません。僕たちはあのドラゴンと共謀していたリリアナを殺すために来ました。ただ、あの人は寝返ったんです」
「そして、ボーラスを実際に殺したのは彼女だった」
「はい、そのとおりです。だから僕は、あの人には贖罪をさせるべきなのかもしれないって思うんです。もしくは、裁判とか。けれどただ殺すというのは……」
そういうテヨの優しさをケイヤはよく心得ていました。彼だけでなくラットも疑問を抱いていることも。けれどこのような暗殺任務は、自分にとって決して珍しいものではありません。リリアナは寝返る前にラヴニカの人々を何百、あるいは何千と殺害したのです。理由があったのかもしれませんし、ボーラスに強いられていたのかもしれない。それでも、そう行動しようと選択したのはリリアナなのです。死に値する行動を選択したのはリリアナなのです――それが現在のケイヤの考え方でした。
というところで、少し先でラットが手招きをしました。ヴェス家の館が見えましたが、ヤヤが説明していた廃墟とはまったく異なっていました。優美に修繕され、明りが点り、着飾った人々が賑やかに出入りしています。場所を間違えたのかとも一瞬思いましたが、それはないとラットが説明しました。
彼女は召使らしき人々を指さし、盗み聞きから察した内容を語りました。彼らは召使というより虜囚、あの金の首輪をつけた主人に支配されている。そして彼らの主人というのは……リリアナ・ヴェスであると。
つまりリリアナはラヴニカの殺戮から逃亡し、故郷へ戻り、そこで大悪人のように人々を使役していた?それならばケイヤにとってリリアナは死すべき存在に違いありません。ラットは安全な侵入経路を見つけると言って再び館へ向かおうとしますが、ふとテヨが何かに気づいたようでした。何か心当たりのある匂いがする、けれど何なのかはわからない……と。少しして、ラットが戻ってきました。そして見てほしいものがあると手招きをします。彼女は大きく迂回して館の背後に広がる庭園へとやって来ました。夜だというのに何人もの召使が働いています。木の間に隠れ、ラットは自分たちに背を向けて作業をしている1人の女性を指さしました。ほかの召使たちと同じく、金の首輪をはめられています。やがてその女性は立ち上がって振り返り、手で汗をぬぐいました。月光に照らされて明らかになったその顔は――リリアナ・ヴェスその人のものでした。
リリアナ・ヴェスが召使の首輪をはめられて生家の庭で働いている。その様子にはさすがのケイヤも戸惑いました。ほかに誰もいないことを確認し、ケイヤは忍び足で近づきます。3人が近づいてもリリアナはまったくの無反応で、素手で雑草をむしっていました。
ケイヤは囁き声でリリアナへと尋ねますが、反応はありません。手を掴んで草むしりを止めさせると、ようやくリリアナは顔を上げました。そこに感情は何もありませんでした。こちらの声が聞こえている様子もありません。手を放すとすぐにこのリリアナは庭仕事を再開しました。ふとテヨはリリアナの衣服に、先ほどと同じ心当たりのある匂いを感じました。煙か香か、ですがやはり思い出せませんでした。
それはともかく、この状況は謎です。リリアナ・ヴェスがこうして召使にさせられているなら、館の女主人であるリリアナ・ヴェスとは一体?ならば自分が探ってくる、とラットが館へ向かい、ケイヤとテヨは再び残されました。
小説「War of the Spark: Forsaken」チャプター48より訳
ケイヤはまだ片手にダガーを握っていた。あえてテヨはそれを顎で示し、尋ねた。「この人を殺すつもりですか?今ならとても簡単かもしれませんが」
彼の想定どおり、この状態のリリアナを殺すのは幽霊暗殺者にとってもどこか不愉快だった。「いいえ。今じゃない。詳しいことがわかるまでは」
テヨは希望を抱いた。ようやく、リリアナ殺害を完全にやめさせるための話ができるかもしれない。
というところで、テヨは1つ閃きました。もしかしたらこの首輪が問題なのでは?ケイヤは止めようとしましたが遅く、彼は手を伸ばしてその留め金に触れました。すると直ちに金の首輪が熱を帯び、リリアナは悲鳴を上げて喉を掴みました。テヨも火傷寸前の手を引っ込めますが、同時にリリアナがテヨの襟元を掴み、脅すように告げたのでした。「何をしてくれるのよ!」
9. ヴェス家の呪い
一方のラット。多くの者の目に見えない彼女は、館に侵入するのも中を捜索するのも簡単でした。誰も気づきません。そして、彼女の目に映る首輪をはめられた召使の扱いはひどいものでした。まるでオルゾフ組のスラルのよう、けれどこちらはれっきとした人間なのに。彼女が持つわずかな精神感応でも、女主人に対する彼らの恐怖がひしひしと伝わってきました。
豪奢な広間へ移動すると、饗宴が催されていました。料理に音楽、華麗な客人たち。そしてその中心に女主人リリアナ・ヴェスがいました。その優雅さとは裏腹に、背後には巨大で醜い2体のゾンビが護衛として立っていました。
ラットは堂々と彼女に近づき、観察します。美しい黒髪、ですがそれ以外は本物のリリアナとは似ても似つきません。庭仕事で土にまみれていても、本物のほうが危険な美しさがあると感じました。ただこのリリアナ・ヴェスは、目が眩むほど大きなサファイアの首飾りを下げていました。
そして、このリリアナは傍らに1冊の書物を携えています。ゾンビを避けて表紙を見ると「ヴェス家の没落」とあります。
ヴェス家の没落。ラヴニカ生まれのラットはもちろん知りませんが、200年ほど前にリリアナがこの地にもたらした惨劇を伝えるものです。そして、この偽リリアナは本物のリリアナではなく、本の表紙に描かれたリリアナ・ヴェスにそっくりなのでした。髪型、衣服まで正確に。唯一の違いは青い宝石の首飾りだけ。
そして宝石といえば、偽者の傍らにはもっと興味深い物体が布に包まれて置いてありました。ラットはその正体を即座に察します。ニコル・ボーラスの角の間に浮いていたあの卵型の石です。プレインズウォーカーの灯を吸収するために用いていたもの。ボーラスが倒されたとき、それは本体と一緒に消滅することなく、リリアナ(本物)が拾い上げていったものです。
ちょうどそのときでした。「Mistress Book Cover/表紙のご婦人」(ラット呼称)が水晶の杯をスプーンで鳴らし、全員の注目を集めました。
小説「War of the Spark: Forsaken」チャプター50より訳
「紳士淑女の皆様。我が屋敷にお招きできましたことを光栄に思います。この折に陰謀団の親睦会を行うのは好ましくない、そう感じている方もおられますね」
そこで言葉が切られると、卓を囲む人々は一斉に異議を唱えた。明らかにそれを待っていた女主人は満足感を見せた。
彼女は続けた。「ほんの最近まで、悪魔王ベルゼンロックのもとで陰謀団は繁栄の頂点にあり、皆様は広大な版図を支配しておられました。あの悪魔が消え去った今、陰謀団の全盛期は終わったとほとんどの皆様は信じていらっしゃいます。ですが今夜お見せしましたように、もう一つの道がございます。正直に申しまして、皆様はすでにこのために動いて下さっておりました。人々を監視し、金を動かし続けました。あの悪魔は行っていなかったことです。皆様こそが、陰謀団の真の英雄なのです」
この言葉にも全員が賛同しました。もちろんラットに「陰謀団」が何なのかはわかりませんでしたが、少なくともいい単語ではないというのは伝わってきました。以下、続きです。
「それでは、何が欠けているのでしょうか?ベルゼンロックが実際にもたらしていたものとは何でしょうか?あの悪魔がただの表看板ではなかったのはいうまでもありません。単純に恐怖を喚起するだけでは足りません。その恐怖を裏付けする力を実際に持つ指導者が必要なのです。民を支配し続けるだけの力を。ベナリア人やセラ教会、そのほか私たちの偉大な行いを今一度挫けさせようとする者から陰謀団を守るだけの力を。そう、私たちです。このカリゴに存在を知らしめる前、私は陰謀団に侵入しました――ええ、侵入です。その価値があるかを見極めるために。価値はありました。私が見た唯一の問題は、ベルゼンロックの気まぐれでした。それが実質的に私たち全員を抑えつけていたのです。今やその問題は消え去りましたが、1つの困難が残っています。その悪魔に取って代わるのは誰なのでしょう?」
その問いかけに広間は沈黙しましたが、1人の男が咳払いをして口を開きました。それは「ヴェス家の呪い」だと。あらゆる子供の悪夢に登場する名前。確かにそれはおとぎ話だと誰もが思っている。ですがどんな大人もかつては子供であり、最悪の恐怖とは幼いころに根付くもの。誰もがリリアナ・ヴェスを怖れている。その証拠に、この地の人々はリリアナ・ヴェスの存在を見せつけられて縮み上がり、ものの数週間で館を再建した。逆らうことなどできないと知っている。何せ、一言でも背信を口にしたなら……喉を焼かれるのだから。
そうして話は続き、全員が陰謀団を称える詠唱を繰り返します。一方ラットは違和感の正体に気付きました。偽リリアナの背後に控える2体のゾンビ、そのどちらもまったく匂いがしないのです。彼女はラヴニカでゾンビをたくさん見てきましたが、完全に腐敗臭のしないゾンビなど存在しませんでした。このゾンビだけでなく、明らかに何かがおかしい。
直観的にラットはそのゾンビに触れようとします。そして思った通り、その手はゾンビをすり抜けました――幻影!しかし、ただの幻影ではありませんでした。ラットのその行動に偽リリアナの首元のサファイアが輝き、青い煙が発せられてゾンビへ入りこむと、それらは固い肉体を得て壁を殴りつけました。そのリリアナもすぐさま立ち上がって辺りを見渡します。侵入者がいる、何らかの魔法で隠れているらしい。彼女はそう客人たちへと告げ、即座に捕らえるよう命じました。
ラットは捕まる心配はしていませんでしたが、それでもここは逃げるのが賢明に思えました。ですがその前に。
同チャプターより訳
ラットはボーラスの宝玉を掴んだ。だがそれに触れるや否や、いくつもの叫びが上がった。「そこだ!」「見つけた!」「ただの小娘だぞ!」そして「泥棒!」何よりも最悪なのは「捕まえろ!」
「リリアナ・ヴェス」はゾンビを進ませ、氷のように冷たい声で言った。
「捕まえなさい。今すぐに」
狼狽したラットは宝玉を落とし、駆けた。
ラットが逃げ出すと、さらなる叫びが響いた。「どこへ行った?」「見失った!」「どの呪文だ?」そして「入口を塞げ!」
「リリアナ・ヴェス」は怒りに金切り声を上げた。
ラットは逃げたが、恐れてはいなかった。真逆だった。陰謀団の何らかの呪文で姿が見えたわけではないと知っていた。
あの宝玉。ニコル・ボーラスのあの宝玉。あれを掴めば……見えるようになる。あの宝玉が……私の呪いを解いてくれる!
10. 標的と追手と
場面は本物のリリアナに戻ります。霞んでいた思考がはっきりし、彼女は目の前の少年に掴みかかりました。
小説「War of the Spark: Forsaken」チャプター51より訳
少年は「その首輪」というような言葉を呟き、リリアナはすぐに手を放して自らの喉を掴んだ。この場所の虜囚としての金属の首輪。この子が!彼女は拳を握りしめ、この少年の魂を抜き取る呪文を唱えた。狙いをつけて魔力を解き放つと、それは少年に襲いかかり――とその瞬間、ギデオンの白いオーラがそれを遮った!
ギデオン?
違う、ギデオンではない。その少年は菱形をした白い光の盾を張っていた。ギデオンの難攻不落のオーラとの偶然の類似か、あるいはリリアナの心にギデオンの存在があったゆえかもしれない。だがこの少年には見覚えがあった。ラヴニカで、自分が従える永遠衆と戦っていた。
私の永遠衆じゃない!ボーラスの永遠衆!
この少年だけではなかった。相棒の女性もいた。そちらはダガーを手に臨戦態勢にあった。
盾の背後から、少年が言った。「その首輪を外そうとしただけなんです」
「本当に?」リリアナは険悪な声色で言った。「私を殺すためにラヴニカから来たんじゃなくて?」
少年と女性は視線を交わします。リリアナの記憶はまだ曖昧でしたが、殺されるつもりもありません。リリアナは屍術の煙を手から放ちましたが、再びその少年の盾に防がれ、続いて彼女は白い光のドームに閉じ込められました。そこで地面に掌をつけ、地下深くを探ります。泥と土のずっと下にあるものを呼び寄せ、顔を上げると白い光の壁の先であの女性が長ナイフを抜いて近づいてきていました。その武器と手は透明な紫色に輝いていました。
同チャプターより訳
「私の合図で球を消して。そうすれば、私はあてがわれた仕事をするわ」
「僕は嫌です」
「テヨ……」
「おふたりをこうして切り離しておくほうが良いと僕は思うんです、せめて全員が落ち着くまでは」
リリアナの思考はまだぼやけていたが、まるでこの少年は自分を守ろうとしているかのようだった。
けれど、それはおかしい。ラヴニカの戦いを生き延びて、リリアナ・ヴェスを守ろうなどと思う者がいるはずもない。
そこで地面から3体のゾンビが湧き出て、2人へと襲いかかりました。少年は思わず悲鳴を上げるも、リリアナを包む光球はなんとか維持していました。彼は後ずさり、女性のほうはというと、襲いかかってきた巨体のゾンビの胸に長ナイフを深々と突き刺しました。屍は顔面から倒れますが、リリアナは3体目を進ませ、それは女性のほうに襲いかかります。しかし、彼女の身体は紫色の霊体と化し、その攻撃はまったく効きませんでした。
少年のほうは盾を張りつつ後ずさりますが、地面から骸骨の手が弾け出て足首を掴みます。彼は小さく悲鳴を上げてそれを振り払おうとし、同時に光の盾は揺らぎ、薄れていきました。長ナイフを構えた女性は、ゾンビの脛を叩き切るとリリアナへと向かってきます。そして光のドームを解くように指示しますが、少年は応じず、必死にゾンビの攻撃を防いでいます。
リリアナもその女性も、タイミングを図れずにいました。ですがやがてゾンビが少年の盾を破壊し、明滅していた光のドームもようやく消えました。そして2人が攻撃に移ろうとした瞬間、背後から何かがリリアナの後頭部を強打し、彼女は意識を失って倒れました。
ケイヤが見ると、リリアナの背後にラットが立っていました。太い木の枝を持って、どこか誇らしげに。枝ではなくダガーを使えば良かったのにとケイヤは言いますが、ラットはそうしたくはありませんでした。リリアナが意識を失い、ゾンビたちは動きを止めます。テヨは足首を掴んだままの骸骨の手をはがそうと奮闘していました。
小説「War of the Spark: Forsaken」チャプター53より訳
憤慨したケイヤが声を上げた。「指示に従わなかったわね!」
「すみません、ですが」
「私が攻撃できたときに盾を切らないで、そうでないときに切った。私たち2人とも死ぬかもしれなかったのよ」
「ラットさんの合図で光球を消したんです」彼はようやく足首を解放した。
「こっちのほうがよかったんですよ」とラット。「ケイヤさんとこの人が戦ったら、3人とも死んでたかもしれないですし――そしたら私は永遠にここに置いてかれちゃいます。それはさておき、本当は今すぐ殺したいわけじゃない、ですよね?」
「まさか」ケイヤはそう言って、ナイフを構えたまま近づいていった。リリアナの隣に膝をつき、ケイヤはその喉元にナイフを突きつけた。首輪の真上に。
「待ってください!」とラット。
「これ以上の好機はないわ」だがケイヤはそこから手を動かしはしなかった――刃を離すことも、喉元を切り裂くこともしなかった。
「そうかもしれません。けど――無防備な女性を殺すのはいいことじゃないって、わかってますよね」
「そうでもないわよ」
「少なくとも、聞いてください。私が見てきたものについて」
ラットは館での出来事を語りました。女主人と客人たち、陰謀団、あの本。サファイアの首飾りとゾンビの幻影。ただ、ボーラスの宝玉については黙っていました。ケイヤはリリアナの喉元にナイフを突きつけたまま聞き、一方のテヨは盛んに大気の匂いをかいでいました。
一通り説明が終わり、そこでテヨははっと気づいて声を上げました。彼がずっと気になっていた何かの匂い、それは「ジンの煙」だというのです。偽者のリリアナ・ヴェスはジンの力を使っていると。
ラットもケイヤもジンが何かを知らず、テヨは説明しました。ジンとは炎や大気の小さな精霊で、ゴバカンでは雲からときどき現れます。それを捕まえることができれば、解放と引き換えに願いを1つ叶えてもらえる。けれどジンは賢くひねくれているため、願いの言葉にはとても気をつけなければいけません。ジンはかすかな煙、香のような匂いを放っているのですが、今感じているそれはとても強い。偽者のリリアナはとても強大なジンをそのサファイアの中に閉じ込め、使役しているのだろう――テヨはそう考えました。
ケイヤは黙ってその説明に耳を傾け、しばし考えていましたが再びナイフへと意識を戻しました。この仕事には関係ないことです。彼女が手に力を込めると、動かず横たわるリリアナの首筋に血が滲みました。
同チャプターより訳
「待ってください!」
テヨとラットは同時に叫び、ケイヤはためらった。とはいえ、それがなぜかはわからなかった。
「まず、あの召使の人たちを助けないと。約束したんです」とラット。
ケイヤはかぶりを振った。「私たちが来たのはリリアナ・ヴェスを殺すためで、カリゴの虜囚を解放するためじゃない」だが彼女はいまだ躊躇していた。
ラットはすかさず言った。「けど誓いましたよね、みんなを守るって。二度とさせないって、覚えてますよね?」
もちろん、覚えている。けれど……
「ヴェスを殺してからその人たちを解放すればいいのよ。本物のヴェスを」
テヨはリリアナを示した。「この人に言い分があるかもしれません」
ケイヤは再び見下ろした。リリアナの目は開かれ、ダガーと幽霊暗殺者を見つめていた。それでも、ケイヤはためらった。
ヴェスは動かなかった。自衛すらしなかった。彼女はただ告げた。「言い分なんてないわ。ただ、1つお願い。あなたたちが私を殺す前に、最後のお願いよ」
11. 続きます&おまけ
だいぶ長くなりましたので、今回はここまでになります。
繰り返しますが、リリアナがボーラスについた理由は本人以外誰も知りません。今回は取り上げませんでしたが、ゲートウォッチ(正確にはジェイスとチャンドラ)もリリアナは有罪だと認識しており、ギルドの決定に苦悩はしますが反発まではしていません。だというのに、ゲートウォッチではない、リリアナと面識すらないテヨとラットがリリアナ暗殺を止めさせようとしているのです。
2人の中にあるのは、若者ならではの純粋な信念。最後の最後にボーラスを裏切ってラヴニカを救ったリリアナを、その背景も何もわからないままに殺していいのかという思いです。ケイヤは職業暗殺者として、そしてラヴニカ出身ではないこともあって割とドライに任務を受け止めていましたが、ティーンエイジャー2人に心を揺さぶられています。
ギデオンはリリアナの善性をずっと信じており、リリアナのほうではそれを冷笑してきました――彼が身代わりになって死亡し、それによって自分が生き永らえてボーラスを倒すまでは。その彼女がテヨとラットの善性に触れて、何を感じるのでしょうか……それは次回に。それにしてもリリアナ、溺れかけたときに見た放浪者さんの白い影(前回参照)に続いてテヨ君の盾にもギデオンを思い出すとは、かなりギデオンの死に苛まれていますよね……。
で、おまけというのは。Forsakenの「リリアナ・ケイヤ編」では、テヨとラットの仲睦まじい様子が何度も語られています。とはいえ出会って数日も経っていない19歳と16歳ですので、そのやり取りはとても微笑ましく。アダルトな展開だったらマジックにも数年に一度あるのですが、こういうのは逆に珍しい。ジェイス&ヴラスカやラル&トミクが遠慮なしの一方で、初々しさを見せてくれます。せっかくですので、これまでの解説でカットしたところを2つ紹介します。
まずはテヨの故郷、ゴバカンに到着した直後のやり取り。
小説「War of the Spark: Forsaken」チャプター27より訳
彼女は辺りを見た。確かにここは庭園、根菜や多肉植物、ぶどうやいくつかの果樹の、丁寧に手入れされた庭園だった。セレズニアほど質は高くないながらも、誰かが、もしくはたくさんの人が維持管理に携わっているのは明らかだった。テヨもその1人なのは言うまでもなく。空は曇った薄い青色で、2つの太陽が地平線のすぐ上にあった。今は早朝か、遅い午後か。え、2つの太陽?
「ここってゴバカンなの?」
「そうです」
「違う世界に来たんだ!」
「わかったでしょう、僕がどう思ってたか」
「すっごい!」
「ゴバカンはラヴニカよりもずっと退屈だって保証しますよ。すぐに飽きてしまうんじゃないかと思います」
「そうかな」
「そうですよ。ラヴニカは不思議なことだらけです。ゴバカンは砂みたいに退屈です。たぶん、僕みたいに」
「君がゴバカンみたいなの?」「ええ。すごく似てます」「つまり私はラヴニカみたいってこと?」「僕にとってはあなたがラヴニカです」ラットは彼を殴りつけたが、まだ力が入らなかった。テヨは声すら上げなかった。「私は不思議なことだらけ?」彼女はそうたずね、顔をそむけた。
「不思議なことだらけです」
彼女は再びテヨを殴りつけた。「何かだらけってことだよね。私たち2人とも」
「会話してるんだろうけど、私には片方しか聞こえないよ」とヤヤ。「それでも、いちゃつくなら別の場所でやってほしいね」
ここはうんざりするヤヤに笑った。もう一つ、気絶したリリアナの隣でジンについて説明する場面です。
同・チャプター53より訳
「待って、ちょっと待って」とケイヤ。「ジンって何?」
テヨとラットはケイヤを見つめ、そしてラットがテヨへと向き直った。「テヨが知っててケイヤさんが知らないことなんてあるの?きみ、ほんっと何も知らないのに」
「やめなさい」とケイヤ。テヨは頷いた。「いえ、本当のことです。僕は本当に何も知らなくて」
「この子2日前まで、ヴィーアシーノもヴィダルケンも見たことなかったんですよ」
テヨはまだ頷き続けていた。「レオニンも。ゴルゴンも。エルフも。そうだ、天使も!」
「あとペガサスとか、グリフィンとか、ゴブリンとか」
「いえ、ゴブリンは知ってました。ゴバカンにもゴブリンはいます。ただ僕は見たことはなくて。ですが――」
「わかったわかった、つまり」ケイヤは不機嫌に言って、いまだリリアナの血を流していないダガーで宙を突いた。「テヨは無知だけど、私はそれを知らないの……それ……」
「ジンですね」とラット。「実を言うと、私も見たことないんです」
「え!?」テヨはひどく驚いた。「僕が知っててラットさんが知らないこともあるんですか?」
「金剛嵐だって昨日まで見たことなかったよ。今日だっけ?なんかもう時間感覚がわかんない」
「それは僕もです」
「いいかげんにしなさい!」ケイヤが叫んだ。「で、ジンって何?」
ナイフを持つ手がプルプルしてるケイヤが思い浮かぶようだ。しばしば不穏な空気の流れるForsakenにて、テヨとラットの2人はいつもほっとさせてくれる存在です。次回分も書き上がっていますので、数日中に掲載されると思います。リリアナ後日談、もう少々お付き合いください。
(続く)